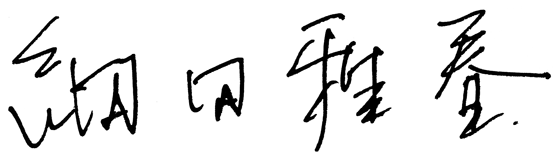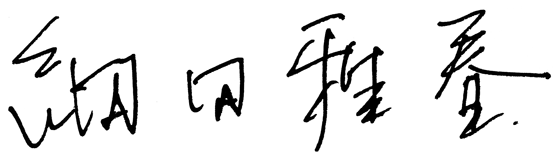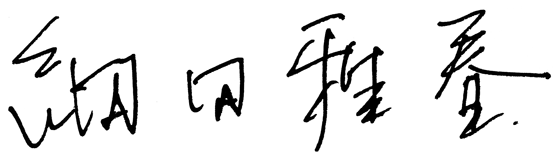海外で仕事をしていると、あまりにも日本の現状との差異を感じてしまう。その最大の理由は、建築としての空間の魅力や形態の主張、独自性のある形についての認識の違いである。建築は都市や社会に新たな可能性を与え、その形(空間)によって都市文化を形成するという役割を果たしていることに対する認識の違いであろうか。
つまり、建築とは何か、という捉え方の違いである。それには建築史の教科書を見ればよいだろう。例えば、ローマ時代のパンテオン、ルネッサンス期のサンタ・マリア・デル・フィオーレ教会、バロック期のサン・ピエトロ寺院、そして近代のル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトなど枚挙にいとまがないが、内部空間のスケール感とその美しさに驚きと感嘆をもってその建築の偉大さを認識する。そして、その外観は個性豊かな形態により、都市の中で圧倒的な存在感を示している。
すなわち、建築の持つ本質は、内部空間の魅力と外観の独自性なのである。その両者の特徴が際立っていることが優れた建築にとっての必要条件である。例えば、建築史的に見て、過去のそれぞれの時代にはそれぞれの「建築様式」があることがその証である。建築様式とは、いわば形態の特徴を鮮明にすることなのである。そして、その様式の中で、いかにして独創的な形態を追求するかが都市における建築の持つ役割ともいえる問題なのである。
平面的な思考と 空間認識の欠如
日本でも、明治・大正期ごろまでの建築にはそうした特徴が反映されていたのだが、戦後の間取りを重視した公団住宅以降、建築からは空間性という概念が失われてしまったように思われる。均一で合理的な間取りばかりが重要視され、それがその後の日本人の建築に対する概念のベースをつくり上げてしまったのではないだろうか。
無論、戦後の混乱期に社会の要請に応えることが建築の優先課題になったのは当然ではあるが、不幸にして、それが建築の主体であるという考えが普遍化してしまったのである。そもそも、日本の建築は常に平面的つながりを基本とした間取り的発想から想を得ており、縦に重ねる立体的な概念は育たなかったともいえる。塔のような例外もあるが、それ自体も、あくまでも平面を積み重ねたものでしかない。
そうしたことを考えるにつれ、若いころイタリアで知り合ったフィレンツェの建築家、ジョバンニ・ミケルッチ氏が「建築は断面だ」と主張していたことを思い出す。断面とは、すなわち、平面では表すことのできない建築の形態と空間のあり様を表すものだ。「建築の形」に対する捉え方について、イタリアと日本との相違を感じたことがいまでも鮮明に記憶に残っている。
建築とは形の魅力 形態が都市に力
いま日本の建築界は、そうした「建築の形」を忘れて、社会的行動を主題としたアクティビティーを表現することに関心があるように感じる。しかし、それだけなら社会心理学や行動科学の話であり、建築の話ではない。端的に言えば建築とは形の魅力であり、その形態が都市に力を与える存在なのである。外形を表すことに興味がない、強い形を持たない建築は、単なる人間の行動パターンや活動領域を表す箱のようなものなのである。そして、その箱をパズルのようにして、さまざまな組み合わせを試みているにすぎない。無論、近代建築を受容する際に生じた、シンプルであることがすべてであるという誤解がいまだ金科玉条のごとく扱われていることも原因の1つではあろう。
無論、常に言い続けてきたとおり建築とは社会の属性であり、建築の形態と空間は、その中で発生するであろう人間の社会的行動に規定されることもまた事実である。しかしながら、ここで強く述べておかねばならないのは、単にそうした規定を満たすだけ、つまり人間の社会的行動の「必要」を満たすだけでは、建築の本質に触れることはできないということである。
なぜなら、人間の社会的行動の多くは日常的な利便性という価値に依存しているからだ。そして、利便性とは自らが体験から導き出した、いわば慣習を前提としているからだ。
最近の建築プロポーザルやコンペの審査でも、利便性について指摘があるばかりで、建築の空間としての魅力や形態のあり様、独自表現など、いわば建築の醍醐味に関わる部分に対しての関心が示されることはほとんどない。いかに優れた「建築」の提案であっても、評価をすることができないのが、悲しいかな現在の審査の現実だと言える。そして実際の建築も、そうした審査の現実を反映して、「建築」とは呼べない建築ができあがってしまうのだ。
利便性超えた欲望が 豊かさをもたらす
ここで、文化人類学者のアンドレ・ルロワ=グーランの指摘を挙げておきたい。ルロワ=グーランはガストン・バシュラールの『火の精神分析』の中の一文「人間は欲望を創造するものであっても、必要を創造するものでは断じてない」に深く同意しながら「欲望が働かない限り我々は著しく人間的なことを何一つおこなわない」と述べている(『世界の根源|先史絵画・神話・記号』ちくま学芸文庫、2019年)。利便性とは日常の行動を規定する「限定的な必要」である以上、それは「著しく人間的なこと」の原因にはならない。言い換えれば、社会的行動を建築にそのまま投影するだけでは、利便性を合理的に満たす箱がつくられるに過ぎないということなのである。
すなわち、利便性を超えた「欲望」があって初めて、建築に豊かさをもたらす形態的回答が生まれてくるということなのである。それこそが、近づきがたい建築の本質へと迫るための必須条件なのである。